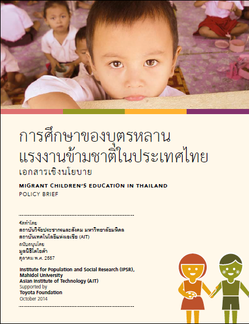プロジェクト成果物レポート
助成プロジェクト「多文化共生社会形成における地方自治体の役割-県/市レベルの移民政策と実践についての日タイ対話」から2つの政策提言が発表されました(国際助成プログラム)
情報掲載日:2015年1月16日

2013年度国際助成プログラムの助成対象プロジェクト「多文化共生社会形成における地方自治体の役割-県/市レベルの移民政策と実践についての日タイ対話」(代表者:日下部京子氏)の成果として、日本・横浜市と、タイ・サムットサコーン県に対して、それぞれ政策提言が出されました。
プロジェクトでは、移民への社会的サービスにおける地方自治体やコミュニティの役割について、横浜市とサムットサコーン県にて現状のレビューを行いました。メンバーの相互訪問や、両自治体の政策担当者、NGOスタッフ、研究者、学校関係者などが参加したワークショップなどを経て、横浜市側は「多文化が共生する横浜を作るために」、サムットサコーン県側は「Migrant Children’s Education in Thailand」として提言が公開されています。
(4月9日追加)
タイのプロジェクトメンバーが制作したアニメーションが公開されました。
日本語字幕版はこちらでご覧いただけます。
横浜市側は、国籍や民族などの違いを超え、地域社会の構成員として共に生きていくような地域づくりを目指す「ヨコハマ国際まちづくり指針」(2006年策定)を前提として、多文化共生政策に関して8つの提言を行っています。例えば、「多様な属性の若者たちが集える『地域の居場所』作り」の重要性を指摘するほか、タイへの現地訪問で移民労働者を多く雇用する企業と、その児童が多く通う学校の関係に直接に学んだことから、「企業の持つ知見やノウハウを支援に活かす仕組みづくり」や「行政と民間団体との継続的な関係づくり」といった点が挙げられています。
サムットサコーン県側では、自治体、企業、NGO、学校によるこれまでの取り組みを分析し、横浜市側のメンバーとの議論も経て、特に移民の児童生徒への教育に着目しました。今後進められることとして、例えば、既にある保健指導員ボランティアと同様の仕組みによって、タイ語が不自由な児童の保護者に対するカウンセリングを行うこと、また、ミャンマー語などを学ぶための学習センターと通常の学校との連携を促進し、両方のニーズに応えられるようにすることを挙げています。
プロジェクトを通じ、状況の異なる2つの地域において、NGO、研究者、自治体関係者等が交流し、現地を訪問して議論が行われました。今後、この提言が活用され、新たなアクションが起こることを期待します。
本プロジェクトの概要は、「助成対象検索」から「D13-N-0026」と入力して検索してください。