プロジェクトイベント・シンポジウムレポート
福島県いわき市において「復興(災害)公営住宅の現状から学ぶ」プログラムを実施(国内助成プログラム東日本大震災特定課題)
情報掲載日:2015年9月2日

 ブリーフィングを行うみんぷく赤池事務局長
ブリーフィングを行うみんぷく赤池事務局長
8月25日(火)〜26日(水)に、トヨタ財団と3.11被災者を支援するいわき連絡協議会(みんぷく)は、福島県いわき市において「復興(災害)公営住宅の現状から学ぶ」プログラムを実施しました。このプログラムの狙いは、次の2点です。
・浪江町、双葉町、大熊町、富岡町から避難してきている原子力被災者(県営復興公営住宅)といわき市地元の津波被災者(市営災害公営住宅)が混在している、複雑ないわき市の状況を、外部のステークホルダーに直に見てもらうことによって理解を深めていただく。
・その上で、いわき市内の復興(災害)公営住宅におけるコミュニティづくりへと向けた効果的な支援の企画立案につなげていただく。
ご参加いただいたのは復興庁、福島県庁、(特活)ジャパン・プラットフォーム、(公財)さなぶり財団などの関係者約10名です。
まず、8月25日(火)の午前中に、参加者に対する、いわき市における復興(災害)公営住宅におけるコミュニティ作りの現状と課題についてのブリーフィングを行いました。続いて、みんぷくがコミュニティづくりの支援に入っている、いわき市営沼ノ内、薄磯団、豊間の各災害公営住宅を実地に訪問し、その現状を見させていただくと共に、自治会関係者から現在のお困り事などを伺いました。
 沼ノ内団地で、自治会関係者から話を伺う参加者
沼ノ内団地で、自治会関係者から話を伺う参加者
ここで、驚いたのは、仮設住宅からこれらの災害公営住宅に入居してきた被災者の方々の内の半数近くの方々が、ここ2,3年のうちに高台の造成が完了次第、そちらに戸建ての住宅を自力で建てられて移転する意向をお持ちであるということです。これに伴い、これらの災害公営住宅が歯抜けの状態になるのではないか、それに伴い共益費の負担が上がるのではないか、といった不安を継続してすまれる予定の方々はお持ちということでした。このこと一つをとっても、復興(災害)公営住宅におけるコミュニティ作りは今後相当な長期間にわたる曲折があろうことが浮かび上がってきました。
26日(水)には、県営下神白団地集会所において、参加者といわき市社会福祉協議会関係者を交えて意見交換会を行いました。ここでは、隣接地に、市営永崎団地が建設され、間もなく入居が開始されるため、福島県庁関係者といわき市関係者の間の連携を深めることが大きな課題となります。この現場の真っただ中にあるという臨場感が幸いし、積極的なやり取りが交わされました。
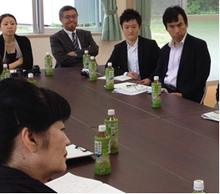 薄磯団地で、自治会関係者の説明に集中する参加者
薄磯団地で、自治会関係者の説明に集中する参加者
その後、いわき市中心部に戻り、復興庁、福島県庁、いわき市関係者に対して、参加者が上記のような復興(災害)公営住宅を実地に見聞した感想を共有し、併せて、いわき市内の復興(災害)公営住宅におけるコミュニティづくりにはいまだ相当な時間がかかるため、関係する部局間での連携を深めてほしい旨、またその為にも、現場感覚が重要と思われることをお伝えしました。
ある復興庁関係者は、「また同種の企画を実施してくれれば、再度参加したい」旨を語ってくださいました。今回のような復興公営住宅におけるコミュニティづくりの課題を現場で見聞するプログラムの有効性を示してくださっているコメントと考えます。
(広報グループ 本多史朗)